Column
投稿日:2021年7月29日/更新日:2022年6月26日

新規に化粧品販売のビジネスを始められる際に、「化粧品を販売するためには、特別な許可が必要になるのか」ということが疑問になるかと思います。
基本的に化粧品販売をする際には、特別な許可は必要ありません。
とはいえ、化粧品の製造や販売にまつわる許可について理解をしている事は、法規リスクを避けるためにも重要なことですので、詳しく解説していきます。
目次
化粧品を製造して販売することに必要な許可は以下の二つです。
以下でこれら2種の認可について、その違いや内容を解説していきます。

化粧品の製造(包装,表示,保管も含む)を行うために必要な許可です。
これには一貫製造工程,部分委受託工程を問いませんので、化粧品の製造の一部のみを行っている場合でも,この許可が必要です。
また、化粧品製造業許可だけでは、製造まではできるものの、完成した製品を市場へと出荷して流通させることが出来ません。

製造によって完成した化粧品を市場に流通させるために必要な許可です。
市場へと出荷された化粧品は、品質面、安全面を含め、化粧品製造販売業許可業者が全ての責任を負うことになります。
そのため、化粧品製造の品質管理及び市販後の製品について管理を行うことが求められます。
上記の通りであれば、新たなビジネスとして化粧品を製造・販売しようとした時には、化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可の2つの取得が必要になります。
そうなると、やはり「許可を取るべきか?」と疑問が浮かぶことかと思います。
しかし、これらの許可を取るのは厳しい規格基準をクリアする必要があり、その準備には莫大な手間と費用を要し、非常にハードルも高いため、現実的ではないでしょう。
そこで、製造販売業許可を持っているOEM会社の出番となります。
最初に記載したとおりに、化粧品の販売においては特別な許可は必要ありません。
しかし、それは国内の化粧品製造販売業許可を持っているメーカーによるOEM製造や、国内の卸業者(ディーラーなど)から仕入れる場合に限ります。
自社で勝手に化粧品の製造を行って販売することや、海外のメーカーから直接仕入れて販売する事などはできないというわけなのです。
そのため、自社でオリジナルの製品を開発して販売したいというときは、必ずOEM会社を活用する必要があります。
さらに、製造販売元の責任の元、製品における品質・安全面の責任はOEM会社が厳格に管理をしているため、安心して製品を開発することもできるわけです。

それでは、販売者として守るべきルールは何でしょうか?
もちろん、ビジネスにおける法規はあらゆるものがあり、何か一つだけを守ればいいというものではありませんが、化粧品販売において販売者が順守すべき主な法規は、薬機法や景品表示法となります。
薬機法とは、
=正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、その名の通り、医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性を確保する他、下記を目的に製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律です。=
薬機法における化粧品の定義は以下の通りです。
=「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。=
これらの薬機法に定められた化粧品の範囲を逸脱した販売をした場合、薬機法違反として行政指導や課徴金などの罰則を科せられるため、しっかりと理解した上で販売をしていく必要があります。
景品表示法とは
=「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止」して「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」を目的としています。=
上記のように、消費者にとって不利益となる販売方法や販促方法を取っている販売会社などを取り締まる法規です。
化粧品や健康食品では、パッケージや広告、販促物、HPやLPにおいても法規遵守に対応していく必要があります。
法規を逸脱すると、薬機法同様に行政指導課徴金、悪質だと審判された場合は懲役などの実刑を課されることもあります。
化粧品を販売していく上では、これらの法規を理解しておくのが良いでしょう。
ここまでの説明を見ると、これだけの法規を気にしながら販売していくのは難しいとお考えになるかもしれません。
もちろん、販売における重要な法規なので、理解をしている必要がありますが、正しい知見を持ったOEM会社に相談することで、これら法規のアドバイスを受けながら製品の開発を行っていくことが可能です。
Held(ヘルト)では多品目の製品設計をおこなってきた実績があります。
法規に遵守した製品設計をおまかせください。
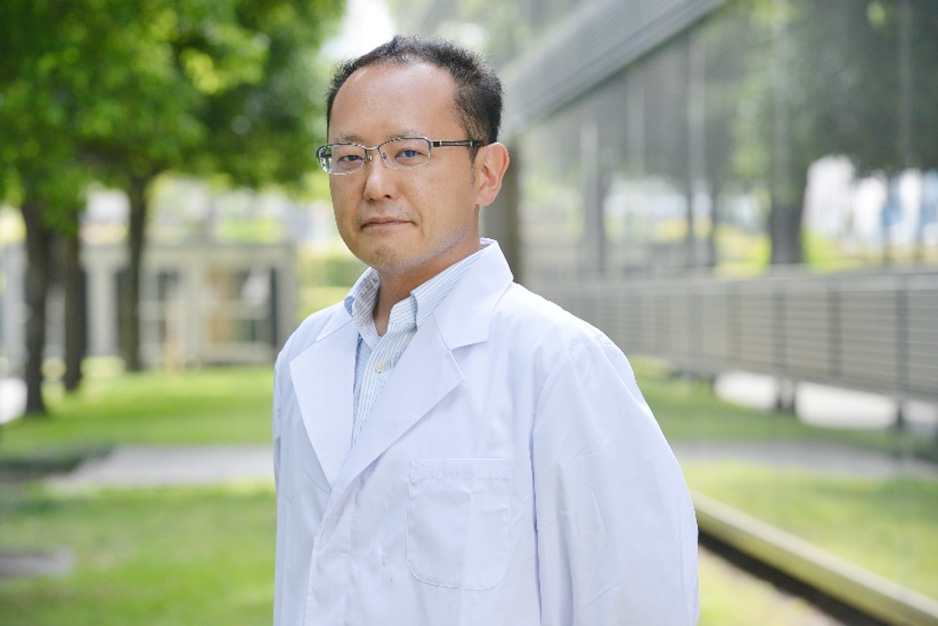
管理栄養士、博士(生物環境調節学)、専門は栄養生理学 千葉 大成
東京農業大学大学院博士課程修了後、国立健康栄養研究所、大学研究機関で、食と健康に関わる研究活動および教育活動に18年携わってきました。研究活動としては、機能性食品素材に着目した骨粗鬆症予防に関する研究を主に行ってきました。一方で、教育活動の傍ら、地域貢献セミナーや社会人教育にも携わってきました。
そういった研究・教育活動から疾病をいかに予防するかを考えるようになりました。つまり、薬剤で“病気にフタ”をすることで病気を抑えることよりも生活習慣(食事、運動、サプリメント)で“病因を流す”ことによって疾病を予防していくことを積極的に働きかけていきたいと考えるようになりました。
2000年東京農業大学農学研究科博士後期課程修了後、2018年まで大学教育研究機関で主にフラボノイドによる骨代謝調節に関する研究に従事した。